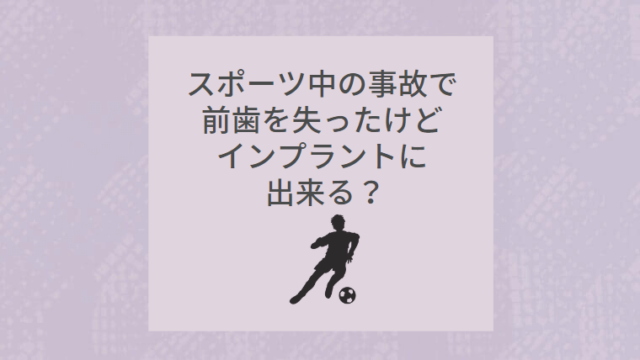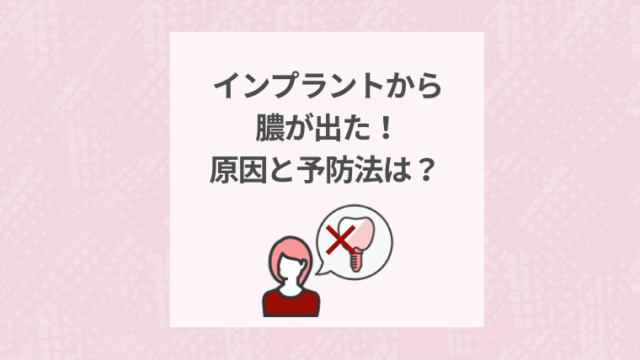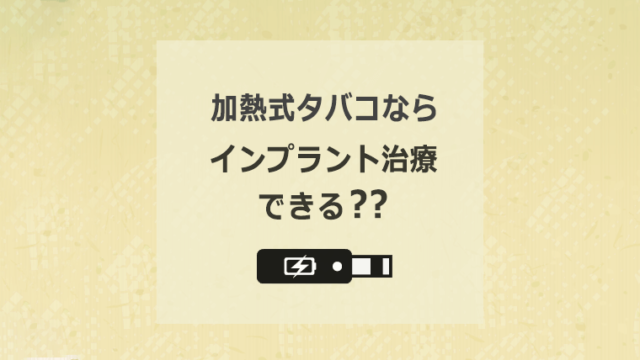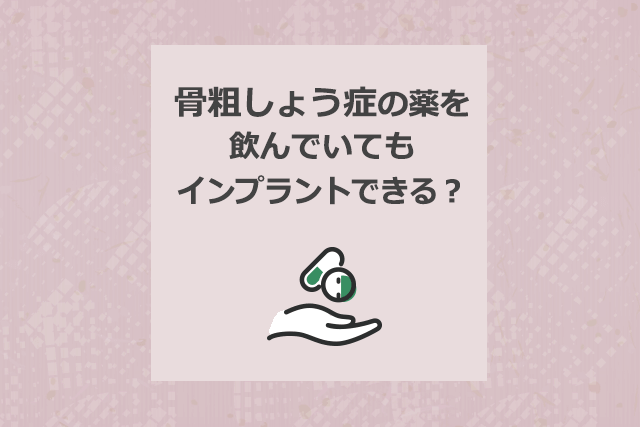
監修・執筆:大阪インプラント総合クリニック 歯科医師 松本 正洋
骨粗しょう症は骨密度が低下し、骨折のリスクが大きくなる病気ですが、インプラントは可能でしょうか? インプラント治療は顎の骨にチタン製の人工歯根を埋め込み、その上に義歯を取り付けます。インプラントと骨粗しょう症についてご説明します。
目次
骨粗しょう症の薬とインプラント治療の関係とは?
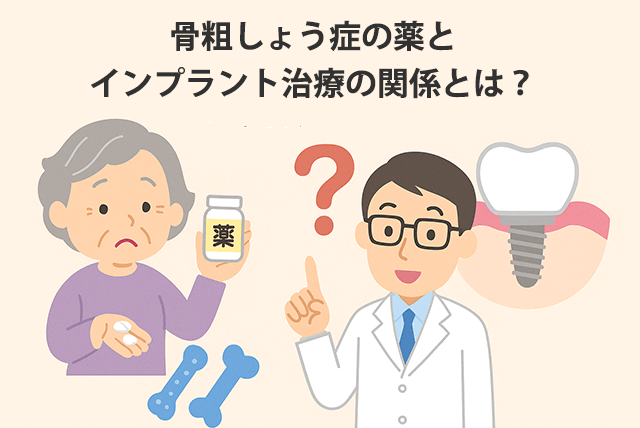
骨粗しょう症の薬を服用している場合、インプラント治療に影響を及ぼす可能性がありますが、必ずしもインプラントができないわけではありません。
1. 骨粗しょう症の薬とインプラント治療のリスク
ビスホスホネート系薬剤の影響
骨粗しょう症の治療には、ビスホスホネート系薬剤がよく使われます。この薬は骨密度を高める効果がありますが、長期間使用することで顎骨壊死(あごの骨の壊死)のリスクが高まることが知られています。顎骨壊死は、インプラント手術後に発生する可能性があり、治癒が遅れることがあります。
デノスマブ
もう一つの骨粗しょう症治療薬であるデノスマブも、顎骨壊死のリスクが指摘されています。この薬も骨代謝に影響を与えるため、インプラント治療には慎重な判断が必要です。
2. インプラントが可能なケース
リスクの評価と管理
骨粗しょう症の薬を服用していても、適切なリスク管理を行うことでインプラント治療が可能な場合があります。治療前に歯科医師と担当医師が連携し、リスクを評価し、治療計画を立てることが重要です。
薬の休薬期間の検討
一部のケースでは、インプラント手術前にビスホスホネート系薬剤の休薬が推奨されることがあります。ただし、休薬のリスクや適切な期間については、必ず内科の主治医と相談する必要があります。
局所的な骨代謝の評価
インプラント埋入予定部位の骨代謝が十分であれば、リスクを最小限に抑えた治療が可能です。CTスキャンや他の画像診断を用いて、顎骨の状態を評価し、インプラント治療が可能かどうかを判断します。
3. 代替治療の検討
他の治療法の選択肢
リスクが高いと判断された場合、インプラント以外の治療法を検討することも一つの選択肢です。例えば、入れ歯やブリッジなどの補綴治療を選ぶことで、顎骨への負担を減らしながら歯の機能を回復することができます。
4. 事前のカウンセリングの重要性
歯科医師との相談
インプラント治療を希望する場合は、事前に歯科医師に骨粗しょう症の薬を服用していることを伝え、治療のリスクについて十分な説明を受けることが重要です。また、治療中の薬に関する情報も正確に伝えることで、適切な治療計画を立てることができます。
骨粗しょう症だと何故インプラントに不向きなの?

何故、骨粗しょう症の患者さんにとって、インプラントは不向きなのかという点についてご説明します。通常はインプラント体と骨が結合するまでに3~6ヶ月程度の期間が必要です。骨粗しょう症の患者さんは骨密度が低いため、通常の2倍程度の期間をかけた方がインプラント体と骨の結合がしっかりと強固なものになり、治療の成功率が高くなります。
そして、治療の為の薬の種類によっては薬剤性顎骨壊死(がくこつえし)のリスクがあるとされています。骨粗しょう症の治療薬としては優秀で、多くの骨粗しょう症の患者さんが使用して骨折などのトラブルを回避することが出来ている薬なのですが、インプラント治療や抜歯は危険だとされています。
骨粗しょう症で服薬中だとインプラントできないわけは?

骨粗しょう症の代表的な治療薬にビスホスホネート製剤(略称:BP製剤)というものがありますが、ビスホスホネート製剤を服用されている方にはインプラント治療が難しくなります。
骨粗しょう症の患者さんはビスホスホネート製剤や、デノスマブが含有されている注射を使用しておられる方がおられます。これらの薬には骨の代謝を抑えてカルシウムの流出を阻止し、骨を固くするという性質があります。骨の代謝を抑えるということは、すなわち新しい骨や歯周組織を作る機能も抑制されます。
そういう方がインプラント治療を行って細菌感染を起こしてしまった場合、細菌の侵入により骨が治りにくくなり、骨が腐る=骨の壊死という最も深刻な合併症の原因になります。
骨粗鬆症の人がインプラント治療で注意すべき主な合併症
1. 薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)
発生しやすい合併症の中心は「薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)」です。
ビスホスホネート製剤やデノスマブ(抗RANKL抗体)など、骨粗鬆症治療薬が原因で顎の骨が壊死しやすくなるリスクがあります。
症状例:歯や顎の痛み、腫れ、歯ぐきから膿が出る、骨の露出、骨折、顎のしびれなど。
2. インプラント周囲炎
骨や歯ぐきが炎症を起こす「インプラント周囲炎」も、骨粗鬆症患者では発生リスクが高くなります。
骨密度が低いため、インプラントの固定力や長期安定性が低下しやすく、周囲炎への進行が早まるケースがあります。
3. 治癒遅延・成功率低下
骨粗鬆症自体やその薬剤の影響で、インプラントと骨が結合しにくく、治癒が遅くなる場合もあります。
特に骨質が著しく悪い場合は、インプラントの成功率が下がるリスクがあります。
合併症リスクを高める要因
- 骨粗鬆症治療薬の種類・服用期間
- 口腔内の衛生状態(歯周病・不良な咬合など)
- 糖尿病、自己免疫疾患などの全身疾患
- 喫煙、栄養不良、人工透析 ※生活習慣や合併する持病
注意・対策
- 薬剤服用歴は必ず歯科医に伝える。
- 定期検診と徹底した口腔ケアが重要。
- 必要な場合は関連科(内科等)とも連携して治療プランを立てる。
骨粗鬆症の方がインプラント治療を検討する際は、予防と術後のフォローをしっかり行うことが合併症リスク低減のカギとなります。
骨粗鬆症患者さんの診療経験から感じる“慎重な判断”の大切さ
これまで多くの骨粗鬆症患者さんのインプラント治療に携わってきました。実感するのは、「治療可否の判断は一人ひとり異なり、非常に慎重な診断と準備が必要」ということです。
たとえば、骨粗鬆症治療薬(特にビスホスホネート製剤やデノスマブ)を服用中の方の場合、薬の種類や服用期間によって顎骨壊死(MRONJ)のリスクが大きく変わります。実際、内科主治医としっかり連携を取り、服薬状況や全身疾患の有無を細かく確認した上で、手術日程の調整や“休薬”の要否を検討したケースも多いです。
インプラント以外の歯の治療法って?
疾患によってインプラントができない方の治療法は、どういうものがあるかご説明します。歯を失われた方には、インプラントの他にもブリッジや入れ歯という選択肢があります。
ブリッジは両隣の歯を削って支台にするため、敬遠される方もいらっしゃいますが、両隣の歯をなるべく削らないというヒューマンブリッジという方法もあります。
また、入れ歯をご検討の際は、是非一度保険適用内で作製することをおすすめします。えづきやで違和感が特に少なければ、自費診療でより薄型の入れ歯を作製し、快適な生活を送ることが可能です。入れ歯を装着すると、歯槽骨の吸収などというデメリットもあります。
骨粗しょう症の薬の服用とインプラントに関するQ&A
骨粗しょう症の患者は骨密度が低いため、インプラント体と骨の結合に通常の2倍程度の時間が必要になります。また、骨粗しょう症の治療薬であるビスホスホネート製剤が骨の代謝を抑制するため、細菌感染による骨壊死のリスクが高まります。
はい、骨粗しょう症の患者でビスホスホネート製剤を服用中の場合、インプラント治療が難しくなります。ビスホスホネート製剤は骨の代謝を抑制し、細菌感染による骨壊死のリスクを高めるため、インプラントの成功率が低下します。
インプラントができない場合、歯を失った方にはブリッジや入れ歯が代替治療法として考えられます。ブリッジは両隣の歯を支台にして補う方法で、ヒューマンブリッジでは歯を削ることを最小限に抑えることができます。入れ歯も自費診療の素材で作製すれば違和感の少ないものが作れますが、歯槽骨の吸収などのデメリットも考慮する必要があります
まとめ

インプラント治療をお考えの方で、骨粗しょう症のお薬を飲まれていたり、注射による治療をされている方は、外科処置によって副作用が出るリスクがありますので、インプラントの初診カウンセリングの際に必ず担当医師にお伝えください。
適切な予防処置、術前術後の管理を行うことで、インプラント手術が可能になる場合もありますので、あきらめずにご相談くださいね。
 医療法人真摯会
医療法人真摯会