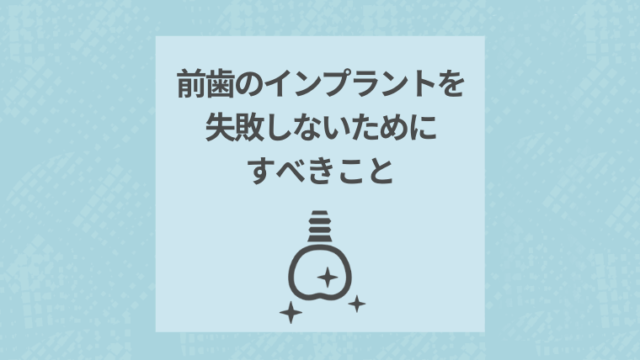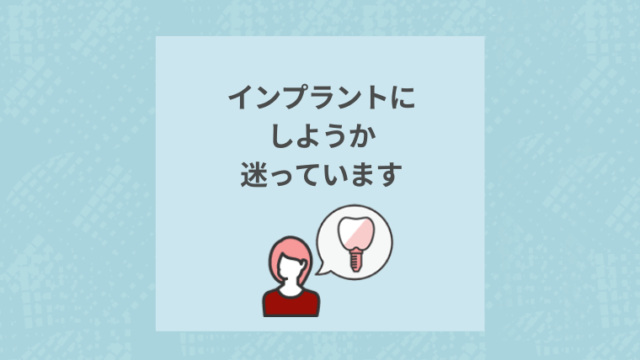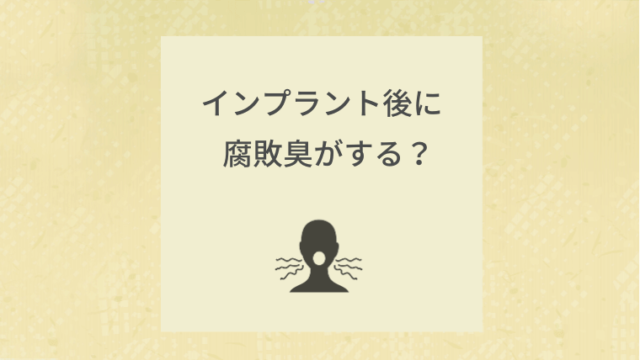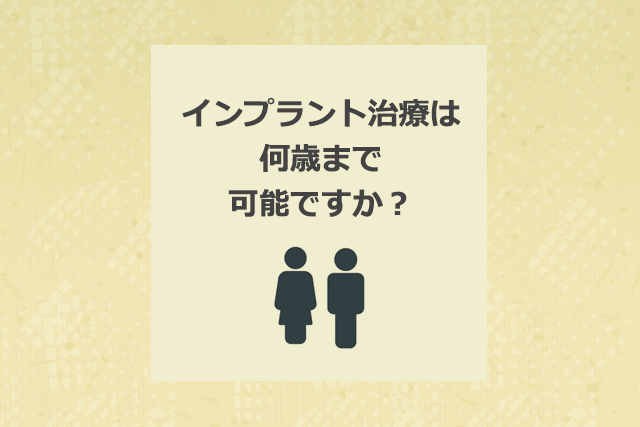
よくいただくご質問の一つに、「インプラントは何歳くらいまで出来ますか?」「高齢者でもできますか?」というものがあります。特に60歳以上の方は、治療できる年齢の上限を気になさっている方が多いようです。
目次
インプラント治療は何歳まで可能か?
1. 年齢の制限はないが条件が重要
基本的にインプラント治療には年齢制限がありません。高齢者でもインプラント治療を受けることは可能です。ただし、治療の可否は年齢よりも患者さんの全身状態や口腔内の健康状態に大きく依存します。
2. 顎骨の健康状態
インプラントを支えるためには、顎骨に十分な量と質が必要です。高齢になると骨密度が低下しやすくなり、インプラント治療を希望されても、すぐに手術が出来ない場合があります。
骨量が不足している場合には、骨移植や骨増生(サイナスリフトなど)の処置が必要になることがあります。これが治療の成功に影響するため、事前の精密な診断が重要です。
3. 全身の健康状態
高齢者の場合、糖尿病や心疾患、骨粗鬆症などの全身疾患を抱えているケースが多いです。これらの疾患は、インプラントの成功率や治癒速度に影響を与える可能性があります。特に糖尿病のコントロールが不十分な場合、インプラント治療後の感染リスクが高まるため、慎重な判断が求められます。
4. 薬剤の影響
高齢者は多くの場合、複数の薬剤を服用しています。特に、骨粗鬆症の治療に使われるビスフォスフォネート系薬剤は、顎骨壊死(骨の壊死)を引き起こすリスクがあるため、インプラント治療を行う前に服用の状況を確認し、必要に応じて医師と相談する必要があります。
5. 手術の耐性
インプラント治療は外科手術を伴うため、高齢者にとっては身体的な負担が大きくなる可能性があります。そのため、患者さんの全身的な健康状態や手術に対する耐性を評価し、必要であれば局所麻酔に加えて静脈内鎮静法(セデーション)と呼ばれる点滴麻酔を行ったり、手術の方法を調整します。
6. メンテナンスの重要性
インプラントを長期間使用するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。高齢者の場合、手や指の機能が低下し、口腔ケアが難しくなることがあります。インプラントを維持するために、歯科医院での定期的なメンテナンスが重要です。
7. 患者さんの意欲と生活の質の向上
インプラント治療を受けるかどうかは、患者さんご自身の意欲や生活の質を向上させる目的によっても決まります。高齢者でも、咀嚼機能を回復させることで食生活が改善し、全身の健康維持につながる場合が多いです。
このように、インプラント治療は年齢に関係なく可能ですが、個々の健康状態や全身疾患、顎骨の状態などを総合的に評価した上で、治療の可否を判断することが重要です。
インプラント治療は一般的には何歳になっても受けられる

実はインプラント治療は、何歳までという風に年齢で決められるものではありません。一般的に、全身疾患や麻酔によるアレルギーや呼吸器の疾患がない方でしたら、どなたでも受けられます。(ヘビースモーカーの方は骨とインプラント体が結合しにくく、傷も治りにくいため、治療の間は禁煙していただく必要があります)
全身の疾患がなければ、90歳の方でも出来ますが、骨量や骨質が足りない場合は、年齢に関わらずインプラントが難しいです。また、高齢者の場合は持病を持っている方の割合が若者と比べて高くなるため、身体へのリスクがあります。
高齢者のインプラント治療のリスクとは?
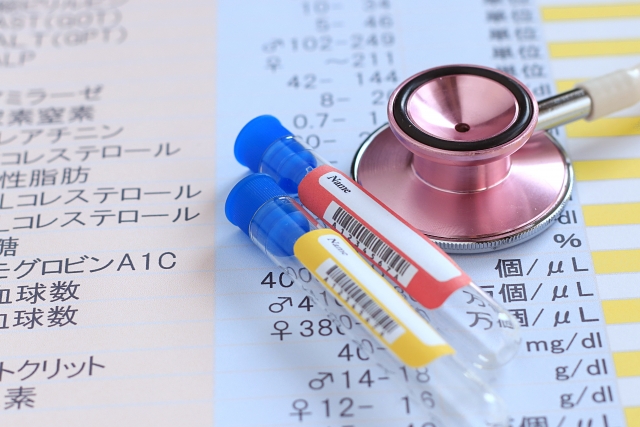
高齢者の方は様々な持病を抱えておられる場合が多く、高血圧、糖尿病、骨粗しょう症等、さまざまです。これらの全身的な症状のある持病を持っておられる方は、インプラント手術を行うことが出来ません。(担当医の指導の下にインプラント治療が可能になる場合もあります。)
更に高齢者の方は免疫が弱く細菌感染を起こしやすかったり、傷を治す能力が低下して傷が治りにくくなっていることがあります。そうなるとインプラントが骨としっかり結合する可能性が低くなり、治療をする上での大きなリスクとなります。
高齢者へのインプラントで特に気をつけるべきポイント
高齢者に対するインプラント治療は、一般的な成人患者さんの場合とは異なる配慮が必要です。高齢者特有の健康状態やライフスタイルを考慮し、治療を計画・実施することが重要です。
1. 全身の健康状態を確認する
高齢者では、糖尿病、高血圧、骨粗しょう症などの慢性疾患を抱えているケースが多いため、以下の点を慎重に確認します。
- 持病の有無・・糖尿病がある場合は、血糖値のコントロールが十分であることが重要です。不安定な状態ではインプラントが定着しにくく、感染リスクも高まります。
- 服用中の薬・・骨粗しょう症の治療に用いられるビスホスホネート製剤を服用している場合、顎骨壊死(顎骨の壊死)が発生する可能性があるため、注意が必要です。
- 全身麻酔や局所麻酔への耐性・・高齢者は麻酔に対する耐性が異なる場合があるため、治療前に麻酔の適応を慎重に評価します。
2. 骨の状態を精密に診断する
加齢に伴い、顎骨の骨密度や厚みが減少することが多く、インプラント治療に必要な骨量が不足している場合があります。
- CTスキャンでの詳細な診断・・骨密度、骨量、神経や血管の位置を把握します。
- 骨造成の必要性・・骨量が不足している場合、骨造成(骨移植やサイナスリフト)が必要になることがあります。
3. 口腔内の環境を整える
高齢者は歯垢や歯石が溜まりやすく、歯周病のリスクが高いことが多いため、インプラント手術前に口腔内環境を整えることが重要です。
- 歯周病の治療・・歯周病がある場合、治療を完了させた後にインプラントを検討します。
- 口腔ケアの指導・・インプラント周囲炎を予防するために、正しい歯磨き方法や定期的な健診の重要性を説明します。
4. 手術後のリカバリーを考慮する
高齢者は、組織の回復力が若年層と比べて低下しているため、術後の管理が重要です。
- 術後の感染対策・・免疫力が低下している場合、感染のリスクが高くなるため、抗生物質の投与や消毒の指導を徹底します。
- 食事や日常生活の配慮・・手術後は柔らかい食事に変更し、無理なく生活を続けられるようサポートします。
5. 高齢者に適した治療計画の提案
インプラント治療が適さないケースでは、他の治療法を検討することも重要です。
- インプラントオーバーデンチャー・・数本のインプラントを用いて取り外し可能な義歯を固定する方法は、高齢者に適している場合があります。
- 入れ歯やブリッジとの比較・・治療効果や費用、患者さんの希望を考慮して、最適な方法を提案します。
6. 心理的なサポート
高齢者の患者さんは、治療への不安や長期的な通院への抵抗感を抱くことがあります。以下の点に配慮します。
- わかりやすい説明・・治療の流れや期間、成功率を具体的に説明します。
- 家族との連携・・患者さんが家族のサポートを受けられるように、家族も交えた相談を行います。
高齢者にとってインプラント治療とは?

高齢になり、若いころのように身体が自由に動かなくなったり、スタミナ不足で活動的ではなくなり、家にこもりがちになる方もおられると思います。そうなった時に、好きなものを味わって食べることは、年齢に関係なく味わうことの出来る幸せの一つといえるのではないでしょうか。
インプラントの最大の特徴は「よく噛める」ということです。高齢でインプラントを希望される方は、若いときには当たり前だった「噛む」という行為が歯を失うことで出来なくなってしまい、何とかもう一度ピーナッツやせんべいなどの硬いものを気にせずバリバリ噛んで食べたいと願っておられます。そんな悩みを叶えてくれるのがインプラントだと言っても過言ではないと思います。
高齢者にとってはしっかり噛むことが何よりも大事

しかも高齢者の方にとって自分の歯でしっかり噛んで食事をすることは、全身の健康や長生きにもつながります。入れ歯になると柔らかい食べ物が中心の食生活となるため、たんぱく質が不足しがちになり、筋力が低下して体力の衰えの原因となります。
また、いつもしっかり噛めない状態で飲み込んでしまうことで、胃の負担になるだけでなく、認知症の発症にもつながるといわれています。
このようにインプラント治療には厳密な年齢制限はありません。インプラントが出来るか出来ないかは、年齢ではなく患者さんの骨の状態によって決まります。
あごの骨が成長している最中の子供はインプラントを避けた方が良いですが、18才以上であれば何才でも治療は受けられます。
まとめ
インプラント治療は、あごの骨の成長が完了した20歳くらいからあごの骨がまだ丈夫な70歳くらいまでがおすすめ出来る年齢となります。しかし年齢に関わらず、骨質や骨量が良好であることと全身の健康状態に問題がなければ、インプラントが可能です。担当の歯科医師とよくご相談され、治療をお決めください。
 医療法人真摯会
医療法人真摯会